高大連携体験授業 令和7年2月18日(火)の受講生を募集します
2025.01.10
高大連携体験授業 令和7年2月18日(火)の受講生を募集します
2025年2月18日(火)「高大連携体験授業」詳細はこちらから
~ 大学の学びとは?! ここであなたの未来を発見しよう! ~
本学では、令和7年2月18日(火)に高大連携体験授業を行います。
植草学園大学の学びを体験して『自分の未来』をイメージしてみませんか?
教職や保育、理学療法、作業療法など様々な分野の生の授業体験ができます!
令和7年度新設の看護学部の学びも先取り!ぜひご参加ください!
また、特別に「教職・公務員支援センター」を開放し、教職・保育担当の教員と学生が、高校生の皆さんからのご相談にお応えし、模擬授業等も企画しています。
お昼は定食ランチが無料です!!
学食(L棟1階Ku-Su Ku-Su)でこの機会にぜひご堪能ください♪希望される場合はご予約をお願いします。(昼食の持参も可能です。)
申込期間
高大連携校・植草学園大学附属高等学校の高校生 令和7年1月15日(水) ~ 令和7年1月23日(木)
すべての高校生 令和7年1月29日(水) ~ 令和7年2月6日(木)
※お申込開始は1月15日(水)からになります。お申込をお待ちしています☆
2025年2月18日(火) 時間割 ※詳細は授業名をクリックしてください
2時限11:00~12:30
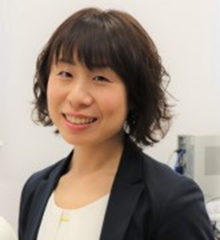 小学校家庭科の授業をつくってみよう家庭科指導法
小学校家庭科の授業をつくってみよう家庭科指導法 発達障害のユニークな世界障害インクルージョン論
発達障害のユニークな世界障害インクルージョン論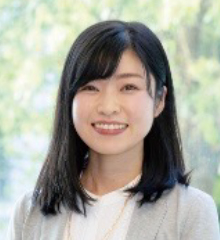 子どもにとって造形表現は
子どもにとって造形表現は
どんな意味がある? 子どもと表現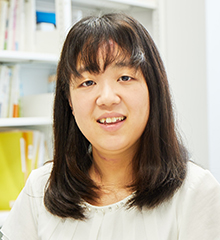 記憶のメカニズムー効果的な勉強方法とは?ー教育心理学・心理学基礎実験Ⅰ
記憶のメカニズムー効果的な勉強方法とは?ー教育心理学・心理学基礎実験Ⅰ 先生になるには?~教育学入門~教育学入門
先生になるには?~教育学入門~教育学入門 明日から使える理学療法士のワザ、教えます!内部障害系疾患理学療法学こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
明日から使える理学療法士のワザ、教えます!内部障害系疾患理学療法学こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました 終末期のリハビリテーションと
終末期のリハビリテーションと
コミュニケーションスキル内部障害と作業療法学 手術を受ける患者の看護急性期看護学概論、成人看護方法Ⅰ・Ⅱを再構成こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
手術を受ける患者の看護急性期看護学概論、成人看護方法Ⅰ・Ⅱを再構成こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
3時限13:20~14:50
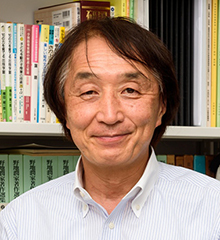 哲学対話をしよう!国語科指導法
哲学対話をしよう!国語科指導法 特別支援教育ってなあに?-知的障害のある子どもたちを支えるために-知的障害教育Ⅰこちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
特別支援教育ってなあに?-知的障害のある子どもたちを支えるために-知的障害教育Ⅰこちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました 赤ちゃんが絵本から学ぶこと子どもと言葉こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
赤ちゃんが絵本から学ぶこと子どもと言葉こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました ストレスに強い心をつくろう自信を高める心理学こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
ストレスに強い心をつくろう自信を高める心理学こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました ~あなたの夢を叶えるために~教職・公務員支援センター 特別開放!
~あなたの夢を叶えるために~教職・公務員支援センター 特別開放! 体幹を操る!姿勢と動作の新発見理学療法評価学
体幹を操る!姿勢と動作の新発見理学療法評価学 ゴムの手が自分の手になる?―錯覚から学ぶ脳の身体認識の仕組み―認知機能と作業療法評価学こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
ゴムの手が自分の手になる?―錯覚から学ぶ脳の身体認識の仕組み―認知機能と作業療法評価学こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 家庭科指導法
- 授業名
- 小学校家庭科の授業をつくってみよう
馬場 彩果
発達教育学部 講師小学校教育コース
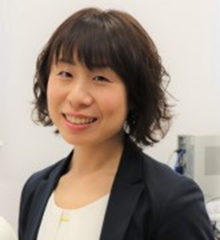
大学では、家庭科を学習する大切さやおもしろさを大学生自身が見つけ、授業づくりを実践しています。そんな大学の授業を体験してみませんか?講義を聞くだけでなく、話し合いをしたり体を動かしたりしながら学びます。小学校の先生をめざしている優しい大学生も一緒ですので、家庭科が得意な人も苦手な人も安心して参加してください!
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 障害インクルージョン論
- 授業名
- 発達障害のユニークな世界
野澤 和弘
発達教育学部 教授特別支援教育コース

発達障害の子どもたちが急増しており、通常学級でも8・8%(11人に1人)に発達障害があるという文部科学省の調査が注目されています。外国では有名な俳優や映画監督やIT企業のカリスマたちに発達障害があることが知られています。できないところばかり日本では注目されますが、彼らの才能を生かすことで社会や経済は大きく変わります。そして、私たちの中にも発達障害の要素はあります。自分自身と社会を深く理解するために、発達障害の世界を知りましょう。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 子どもと表現
- 授業名
- 子どもにとって造形表現はどんな意味がある?
畑山 未央
発達教育学部 助教幼児教育・保育コース
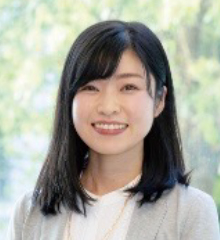
保育現場で造形表現をしている子ども達を思い浮かべてみてください。絵を描いている?粘土で製作?そのときの保育者の関わりは?子どもが表現することは、その子自身や生活、人生にどんな意味があるのでしょうか。
私が保育現場で出会うのは、教えられた通りに描くのではなく、決められた通りにつくるでもない、「やりたい!」から出発して、小さな手から力いっぱい生み出された宝物たちを手に「見て!」と笑顔を見せる子どもたちです。
皆さんと一緒に「子どもの造形表現」を捉え直してみたいと思います。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 教育心理学・心理学基礎実験Ⅰ
- 授業名
- 記憶のメカニズム ー効果的な勉強方法とは?ー
北田 沙也加
発達教育学部 講師発達教育心理コース
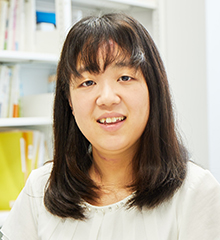
私たちがどのように知識や出来事を記憶し、思い出しているのか、簡単なゲーム等を取り入れながら、記憶のメカニズムについて解説します。記憶と心理の関係性について理解を深め、効果的な勉強方法について考えてみましょう。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 教育学入門
- 授業名
- 先生になるには?~教育学入門~
小野 まどか
発達教育学部 講師一般教養

植草学園大学では小学校・特別支援学校・幼稚園だけでなく保育園や音楽療法の先生になる人を養成しています。そもそも先生になるためにはどんな知識が必要なのか学んだり考えたりするのが「教育学入門」です。この授業は本学1年生の多くが受講しており、先生になるための入門的な内容を学ぶことができます。将来の進路が決まっていなくても、「先生」は身近な存在。「先生」ってどうやってなるのかな?一緒に考えてみませんか?
【準備するもの】
筆記用具
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
2限
- 分野
- 内部障害系疾患理学療法学
- 授業名
- 明日から使える理学療法士のワザ、教えます!
松岡 瑞雄
保健医療学部 講師理学療法学

動物は、血液を送る心臓や酸素を取り込む肺、解毒する肝臓、尿をつくる腎臓といった内臓器が働いてくれるので元気で生活ができます。したがって、この臓器のどこかが故障すると集中的な治療が必要となります。治療中はどうしても体を動かす機会が少なくなってしまい、瘦せ細り、疲れやすい状態になってしまいます。本科目では、そのような患者さんが少しでも早く回復するとともに、再発を予防するために必要な知識を学びます。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 内部障害と作業療法学
- 授業名
- 終末期のリハビリテーションとコミュニケーションスキル
百田 貴洋
保健医療学部 教授作業療法学

がん末期の人へのリハビリテーションを通じて、命について考える機会とし、自身の死生観を深めるとともに、コミュニケーション・スキルについて実践を通して、理解を深めます。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
2限
- 分野
- 急性期看護学概論、成人看護方法Ⅰ・Ⅱを再構成
- 授業名
- 手術を受ける患者の看護
小西 美ゆき
保健医療学部 講師令和7年度看護学部 准教授
看護学

全身麻酔で手術を受ける患者さんの身体の中では、手術を受ける臓器以外にも全身にさまざまな変化が起こっています。看護師は手術の後、どのようなことに注意しながら患者さんの観察やケアを行っているのでしょうか。
2年生から3年生で学ぶ、手術を受ける患者さんの看護の講義と演習の内容を、ダイジェストで体験します。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 国語科指導法
- 授業名
- 哲学対話をしよう!
横田 敬一郎
発達教育学部 教授小学校教育コース
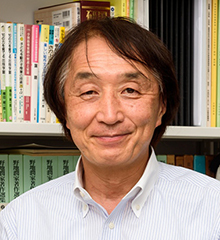
哲学対話のルールは、①何を言ってもいい。②人の言うことに対して否定的な態度をとらない。③発言せず、ただ聞いているだけでもいい。④お互いに問いかけるようにする。⑤知識ではなく、自分の経験に即して話す。⑥話がまとまらなくてもいい。⑦意見が変わってもいい。⑧分からなくなってもいい。の8つだけです。自分たちで問いを出し合って、おしゃべりしましょう。「スポーツについて」、「友情について」、「金子みすゞの詩を読む」の3つの対話を予定しています。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
3限
- 分野
- 知的障害教育Ⅰ
- 授業名
- 特別支援教育ってなあに? - 知的障害のある子どもたちを支えるために -
髙瀬 浩司
発達教育学部 准教授特別支援教育コース

特別支援教育は、特別な支援を必要とする子どもたちの自立や社会参加に向けて、全ての学校で大切にされています。中でも、知的障害のある子どもたちの多くが、特別支援学校等で学んでいます。ハンディキャップのある子どもたちですが、適切な教育や支援をとおして、持てる力を存分に発揮することができるようになります。この授業では、知的障害のある子どもたちや具体的な支援方法などについて学んでいきます。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
3限
- 分野
- 子どもと言葉
- 授業名
- 赤ちゃんが絵本から学ぶこと
栗原 ひとみ
発達教育学部 教授幼児教育・保育コース

「子どもと言葉」の授業は、子どもたちがどのように言葉を獲得していくのかを学ぶ科目です。絵本から「ことばの前のことば」の世界を赤ちゃんが豊かに楽しんでいることをご存じですか。皆さんも一緒に赤ちゃん絵本で「ことばの前のことば」の世界を体験してみましょう。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
3限
- 分野
- 自信を高める心理学
- 授業名
- ストレスに強い心をつくろう
足立 英彦
発達教育学部 准教授発達教育心理コース

人生の中で、ストレスは急激に増えたり、気づかないうちに蓄積していったりして心や体の健康に悪影響を与えることがあります。今、ストレスをそれほど感じていない、という人も、今後のため、自分の力をさらに引き出すために、ストレスやその対処法について学んでおくことが役立ちます。この授業では、ストレスに対する様々な対処法について考え、ストレスを和らげる新しいスキルを練習します。ストレスへの対処法について、少しだけグループディスカッションも行います。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 教職・公務員支援センター 特別開放!
- 授業名
- ~あなたの夢を叶えるために~
特命教授
教職・公務員支援センター
「教職・公務員支援センター」を開放して、教職・保育担当の教員と学生が高校性の皆さんからのご相談にお応えします。
大学生と一緒に模擬授業も企画しています。
将来、教員や保育士、公務員をめざす方、興味がある方、ここに集まれ~!
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 理学療法評価学
- 授業名
- 体幹を操る!姿勢と動作の新発見
石渡 正浩
保健医療学部 講師理学療法学専攻

この講座では、「体幹」に焦点を当て、体幹を操作することで姿勢や動作がどのように変化するのかを体験的に学びます。座位姿勢を中心に、実際の動きを通じて正しい姿勢を保つための体幹の使い方を探り、効率的な動作のポイントを掴みます。また、これらの知識を日常生活やスポーツにどのように応用できるのかについても解説します。自分の身体と向き合い、新たな発見を通じて健康的な動作の基礎を学ぶ実践的な授業です。
高大連携体験授業(2025年2月18日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
3限
- 分野
- 認知機能と作業療法評価学
- 授業名
- ゴムの手が自分の手になる? ―錯覚から学ぶ脳の身体認識の仕組み―
大平 雅弘
保健医療学部 講師作業療法学専攻

この錯覚は、ラバーハンド錯覚といいます。
以前、TikTokでバズったこの再現動画を見たことがある人もいるかもしれませんね。
この錯覚を体験しながら、脳の仕組みとリハビリについてわかりやすく解説します。
お申し込みは終了いたしました。

