高大連携体験授業 令和7年7月22日(火)の受講生を募集します
2025.05.30
高大連携体験授業 令和7年7月22日(火)の受講生を募集します
2025年7月22日(火)「高大連携体験授業」詳細はこちらから
~ 大学ってどんなことを学ぶの?
大学生と一緒に体験してみませんか ~
本学では、令和7年7月22日(火)に高大連携体験授業を行います。
大学生と一緒に植草学園大学の学びを体験して『未来の自分』をイメージしませんか!
教職や保育、理学療法、作業療法、看護など様々な分野の生の授業体験ができます!お昼は定食ランチが無料です!学食(L棟1階Ku-Su Ku-Su)でこの機会にぜひご堪能ください♪希望される場合はご予約をお願いします。(昼食の持参も可能です。)
申込期間
高大連携校(26校) 令和7年6月1日(日)~令和7年6月13日(金)
全ての高校生 令和7年6月19日(木)~令和7年7月3日(木)
※お申込開始は6月1日(日)からになります。お申込をお待ちしています☆
※第一希望講座が定員に達し次第、第二希望講座に変更になる場合があります。予めご了承ください。
2025年7月22日(火) 時間割 ※詳細は授業名をクリックしてください
2時限11:00~12:30
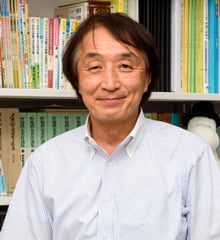 教科学習・学級経営で活用できるボードゲーム専門ゼミナールⅠ
教科学習・学級経営で活用できるボードゲーム専門ゼミナールⅠ 大学のゼミを体験しよう~特別支援学校授業研究会報告会~専門ゼミナールⅠ・Ⅱ
大学のゼミを体験しよう~特別支援学校授業研究会報告会~専門ゼミナールⅠ・Ⅱ 保育を楽しもう~!専門ゼミナールⅡこちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
保育を楽しもう~!専門ゼミナールⅡこちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました 教育・保育に活かせる心理学~“こころ”がわかる人になるために~専門ゼミナールⅡ
教育・保育に活かせる心理学~“こころ”がわかる人になるために~専門ゼミナールⅡ 先生ってどんな仕事?~現場の様子を覗いてみよう~教職原論こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
先生ってどんな仕事?~現場の様子を覗いてみよう~教職原論こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました 手足を動かす脳と神経の仕組み成人中枢神経系疾患理学療法治療学実習
手足を動かす脳と神経の仕組み成人中枢神経系疾患理学療法治療学実習 脊髄損傷者の生活を支える作業療法身体機能と作業療法治療学Ⅰ
脊髄損傷者の生活を支える作業療法身体機能と作業療法治療学Ⅰ フローレンス・ナイチンゲールの生涯と業績看護学原論Ⅰ
フローレンス・ナイチンゲールの生涯と業績看護学原論Ⅰ 乳児の身長・体重を測ってみよう!小児看護学概論
乳児の身長・体重を測ってみよう!小児看護学概論
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 専門ゼミナールⅠ
- 授業名
- 教科学習・学級経営で活用できるボードゲーム
横田 経一郎
発達教育学部 教授ゼミ
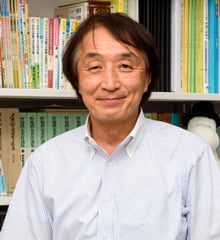
本ゼミ生の2人が、卒業研究としてボードゲームをテーマにしようとしています。そこで、教科学習・学級経営で活用できるボードゲームで実際に遊び、どのような学力形成や教育効果が望めるかを検討します。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 専門ゼミナールⅠ・Ⅱ
- 授業名
- 大学のゼミを体験しよう ~特別支援学校授業研究会報告会~
髙瀬 浩司
発達教育学部 准教授特別支援教育コース

大学のゼミってどんなことをするの?髙瀬ゼミは、特別支援教育・知的障害教育が専門分野。特別支援学校教員を目指す学生が、多く在籍しています。「現場から学ぶ」をモットーに、自分自身の興味・関心に基づく研究テーマや課題を追求していきます。4年生達はゼミのフィールドワークで、特別支援学校授業研究会(7月上旬)に参加予定。今回の授業では、実際の研究授業の報告やディスカッションを通して、仲間と共に学生の視点で授業づくりや支援の在り方を考えます。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
2限
- 分野
- 専門ゼミナールⅡ
- 授業名
- 保育を楽しもう~!
栗原 ひとみ
発達教育学部 教授幼児教育・保育コース

保育は計画によって営まれています。計画は子どもの姿から立ち上げていきます。学生ですので、子どもの姿からの計画立案は難しいのですが、子どもの発達段階などから目標を定めて、仮説を立てていきます。そのことを模擬保育と呼びます。専門ゼミナールⅡの4年生が5歳児7月を想定した模擬保育を実践していきます。皆さんは5歳児の園児になった気持ちで参加してくださいね。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 専門ゼミナールⅡ
- 授業名
- 教育・保育に活かせる心理学 ~“こころ”がわかる人になるために~
金子 功一
発達教育学部 准教授発達教育心理コース

本授業では心理学の知見を体験しながら楽しく勉強します。受講者数に応じて、グループワークも実施します。是非参加してみてください。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
2限
- 分野
- 教職原論
- 授業名
- 先生ってどんな仕事? ~現場の様子を覗いてみよう~
小野 まどか
発達教育学部 講師小学校・特別支援教育コース

そもそも先生ってどんな仕事をしているのでしょうか?普段、先生の様子を何気なく見ていても、じっくり観察することはないのではないでしょうか?この授業では「教職原論」という教員になるために必要な法律や規範等を学びますが、7月22日の回では実際の先生の動きを観察し、子どもに対してどのような声掛けをしているのか、どのような働きかけをしているのかを映像を見ながら学んでいきます。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 成人中枢神経系疾患理学療法治療学実習
- 授業名
- 手足を動かす脳と神経の仕組み
倉山 太一
保健医療学部 教授理学療法・神経科学

人間は脳から電気信号を出して手足を動かします。また、筋肉の特定の場所を軽く叩くと、電極をつけなくても脊髄に電気信号を送ることができ、脊髄がそれに対して反応するという不思議な現象を観察することができます。さらに最近では磁力を利用して脳に直接電気を流し、手足を動かすことができる機械も作られています。
本講義ではそれらのデモンストレーションを通じて、人体の機械的側面をご説明します(本学学生がサポートします!)。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 身体機能と作業療法治療学Ⅰ
- 授業名
- 脊髄損傷者の生活を支える作業療法
池田 恭敏
保健医療学部 教授作業療法学専攻

脊椎を骨折したり脱臼すると、その中の脊髄が損傷され、手足が動かせなくなります。そのような脊髄損傷者がどのように日常生活を再獲得し、社会復帰して就労や趣味を再開していくのか。その作業療法プロセスや、福祉用具・ロボットテクノロジーの活用を解説します。また、東京パラリンピックを契機に認知度が高まっている車いすバスケットボール、車いすテニス、車いすラグビーについて、ルール、用具、クラス分けを解説します。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 看護学原論Ⅰ
- 授業名
- フローレンス・ナイチンゲールの生涯と業績
永田 亜希子
看護学部 准教授看護

近代看護を確立し、看護職を専門職と位置付けたフローレンス.ナイチンゲールは、クリミア戦争に従軍し、スクタリの野戦病院で負傷兵の看護に始まり、フ病院統計の標準化、英国陸軍の衛生改革、看護師・助産師学校の開講、植民地の改革など数多くの改革を実施してきました。その内容と背景について、当時の世界情勢を踏まえて、解説し、ナイチンゲールが現代に残してくれているメッセージを紐解きます。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
2限
- 分野
- 小児看護学概論
- 授業名
- 乳児の身長・体重を測ってみよう!
中水流 彩
看護学部 准教授看護

林 ひろみ
看護学部 教授看護

中村 伸枝
看護学部 教授 学部長看護

赤ちゃんが生まれてから1歳になるまで(乳児)の発育を把握することは、病気の有無によらず、とても大切なことです。看護師や保健師が、乳児の身長や体重を測りながら、発育をどのように診ているかミニ講義と、体験を通して学びます。赤ちゃんの身長や体重を正確に、安全に測定する方法を、着替えやおむつ交換も含めて体験します。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 特設:算数科教育通論
- 授業名
- 一筆書きにチャレンジ!!
小坂 裕皇
発達教育学部 教授小学校教育コース

一筆書きができるかどうかには決まりがあります。簡単な場面から導いていってその秘密を探ります。ぜひ一緒にやってみませんか?秘密がわかったら友達や家族と楽しんでみてはいかがでしょうか。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 肢体不自由教育課程論・指導法
- 授業名
- 肢体不自由のある子どもの指導法
渡邉 章
発達教育学部 教授特別支援教育コース
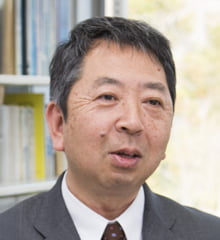
肢体不自由のある子どもにはどのような特徴があり、どのような支援が必要なのか。どのような教材・教具の工夫が必要なのか。子どもの発達段階を踏まえた支援はどのように行えば良いのか。模擬授業を通して授業改善に役立つ視点を身につけます。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 保育原理
- 授業名
- 保育士になった自分
小川 晶
発達教育学部 教授幼児教育・保育コース

「保育」とはなにかを知るために、法律や制度、思想や知見などを学んできました。また、子ども観や保育観の昔と今、変容のプロセスに触れて、自身で考えてみることもしてきました。保育者が子どもの育ちをどう支えるのか、その子自身の形成にどう重要なのか、これまでの授業を振り返りながら、さらに考えていきます。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
こちらの講座は定員に達しましたので募集を締め切りました
3限
- 分野
- 専門ゼミナールⅡ
- 授業名
- 目の錯覚現象の体験
清末 有紀
発達教育学部 助教発達教育心理コース

人は見たり聞いたりすることで周りの環境の情報を取り入れています。今回は目の知覚(視覚)を代表に普段私たちがどのように世界を認識しているのか、そして目の錯覚現象について体験しながら学んでもらいたいと思います。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- インターメディエイトセミナー
- 授業名
- リハビリ専門職とパラアスリートの両立
松本 武尊 氏 (特別講師)
保健医療学部理学療法学専攻、作業療法学専攻


私は陸上競技に励んでいた高校2年の夏に病気になり、両手足が麻痺する障がいを負いました。将来への不安を抱えながらもリハビリを頑張り、麻痺は残りましたが復学して陸上部にも復帰できました。その後、パラ陸上の選手と作業療法士になるための勉強をハードながらも両立させ、現在は作業療法士とパラアスリートとして日々奮闘しています。現在に至る私の経験をお話しします。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 人体の構造の機能演習
- 授業名
- 聴診器を使って、様々な音を聴いてみよう
永田 亜希子
看護学部 准教授看護

阿部 由喜湖
看護学部 講師看護

中條 華子
看護学部 助教看護

看護師は、様々な手段を使って患者についての情報を収集します。今回は聴診器を用いて聴取することができる音(血圧、呼吸音、腸蠕動音)を聴いていただくことで、音が示す身体状態を予測することを学習していただきます。
高大連携体験授業(2025年7月22日(火)開催)のご案内
3限
- 分野
- 小児看護学概論
- 授業名
- 乳児の身長・体重を測ってみよう!
中水流 彩
看護学部 准教授看護

林 ひろみ
看護学部 教授看護

中村 伸枝
看護学部 教授 学部長看護

赤ちゃんが生まれてから1歳になるまで(乳児)の発育を把握することは、病気の有無によらず、とても大切なことです。看護師や保健師が、乳児の身長や体重を測りながら、発育をどのように診ているかミニ講義と、体験を通して学びます。赤ちゃんの身長や体重を正確に、安全に測定する方法を、着替えやおむつ交換も含めて体験します。
お申し込みは終了いたしました。

